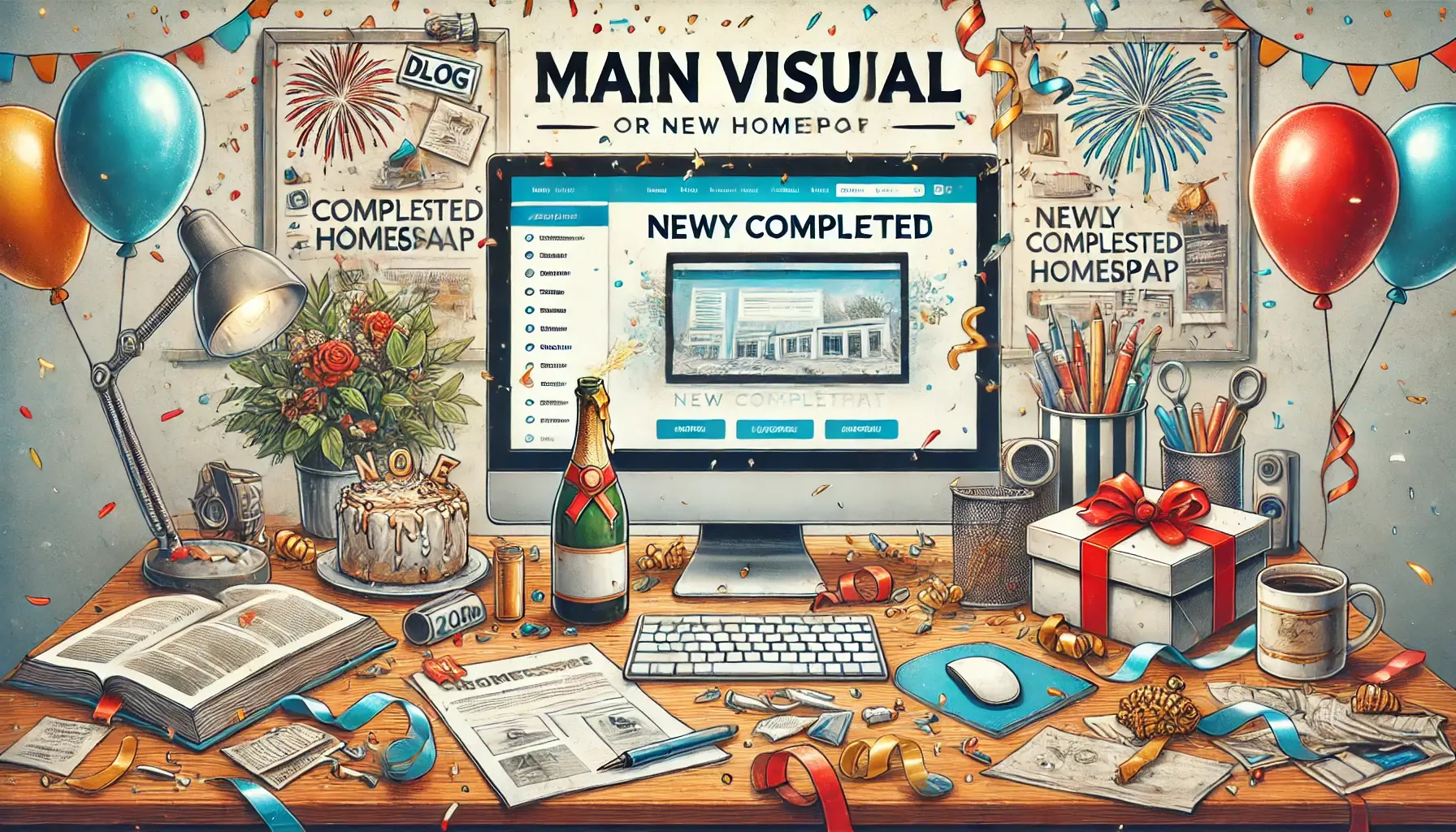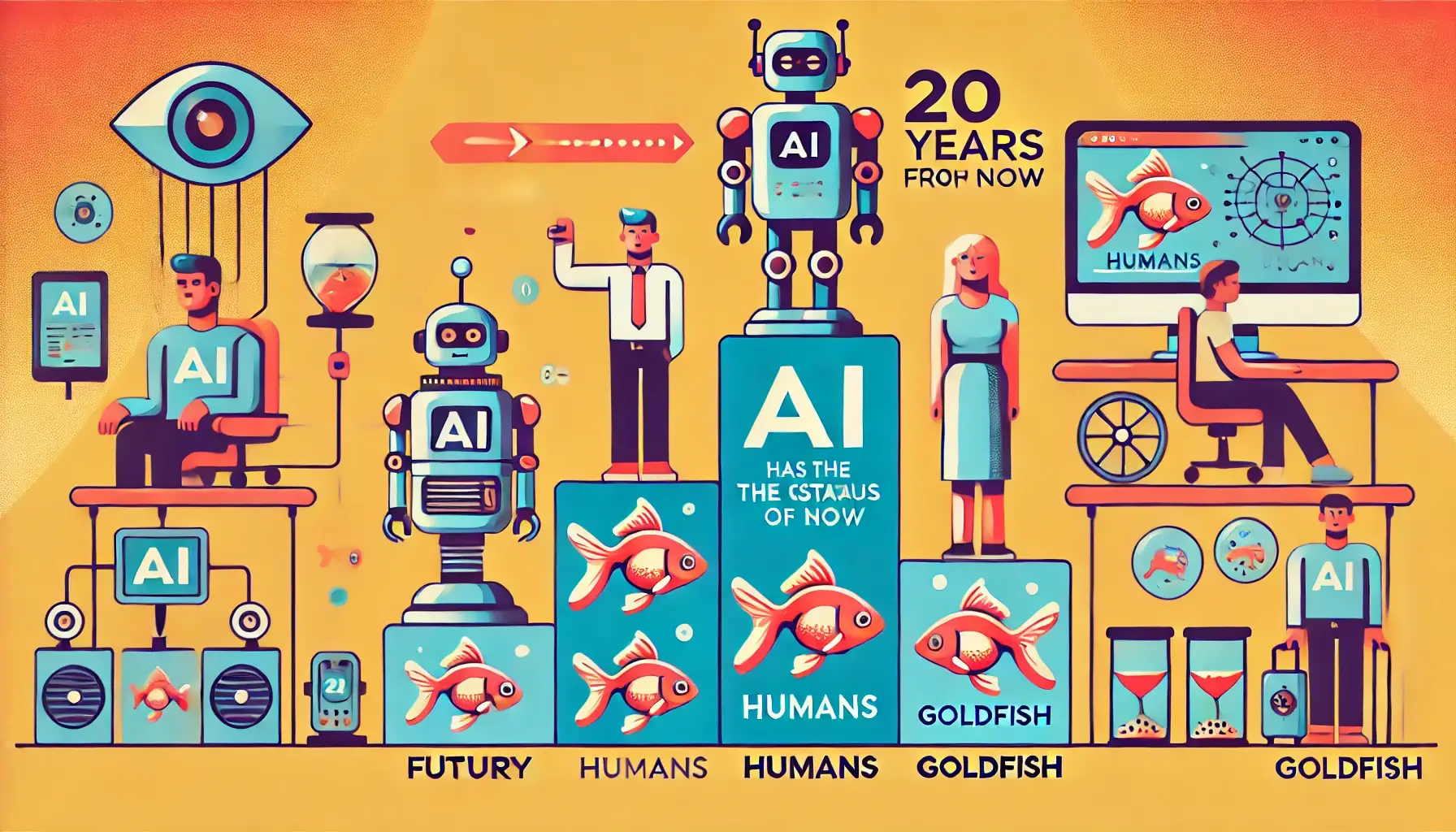
- AIの進化と人間の生きる道
- Iの進化がWeb制作の現場にもたらす変化とは?
- 企画・要件定義
- コンテンツ制作
- デザイン
- 開発(コーディング)・テスト
- サーバー構築・デプロイ
- 保守・運用
少し前になりますが、AI関連事業の打ち合わせの場で、二人の経営者にこんな動画を勧められました。
「AIを世界一活用する企業に ソフトバンクGの孫氏が講演」
この講演で、聴講者の大多数がAIを活用できていないと知った孫会長は、強烈なメッセージを投げかけます。
「あなたたち、このままだと金魚になるよ」
AIは、10年後には人間のあらゆる知的活動を担い、20年後には人間の一万倍の英知となると言います。金魚は人間の知能の一万分の一。つまり、20年後にはAIにとっての人間が、人間にとっての金魚になるというのです。
恐ろしすぎる・・・
今のうちにAIを活用する術を身につけてAIと共存する道を選ぶのか、それを放棄し金魚になってしまうのか? 実感は湧きませんが、無視はできない、とても考えさせられる講演内容でした。
金魚にはなりたくない! そう思った方はぜひ動画を視聴してみてくださいね。
AIの進化がWeb制作の現場にもたらす変化とは?
ここからが本題です。我が社が身を置くWeb制作という業態で、AIがもたらす変革とは一体どの様なものなのでしょうか?
想像してみました。
企画・要件定義
クライアントへのヒアリングを通じて、Webサイトを制作する目的やビジネス上のゴールを明確にする。
マーケットやターゲットユーザの分析、競合調査を行い、サイト構成やデザインの方向性を定める。
AIがクライアントへのインタビューを行い、自動で要件を収集して整理。
AIがリアルタイムに市場分析を行い、最新トレンドが加味されたWebサイトの企画書を自動作成。
コンテンツ制作
撮影を行い、編集作業を通して、画像や動画コンテンツの制作を行う。予算が限られるプロジェクトの場合は、素材サイトから画像や動画を購入する。
クライアントへのインタビューを通じて、テキストコンテンツを作成する。検索からの集客を強化したい場合は、SEOを考慮したライティングが必要となる。
AIがクライアントへのインタビューを通じて、あらゆる種類のコンテンツ案を自動生成。もしくは、クリエイターのアウトプットを分析し、改善案を提示。
各ユーザの特性を理解し、パーソナライズされたコンテンツをリアルタイムで配信。
映像やグラフィックデザイナー、ライターといったクリエイターは、AIのサポートを受けながら、よりクリエイティブな作業に集中できるようになります。予算が限定される小〜中規模サイトにおいては、クライアントが直接AIとやり取りをして、コンテンツ作成を完結させる事ができるかもしれません。
デザイン
サイトレイアウトを決定するために、ワイヤーフレームを作成。
ワイヤーフレームに装飾を加え、デザインのモックアップを作成。
ページ遷移やホバー・クリックアクションなど、ユーザーインタラクションを含むプロトタイプを作成。
参考サイトをいくつかピックアップすると、AIがデザインのモックアップ・プロトタイプを自動生成。
AIへのフィードバックと対話を通じて改良を重ね、最終的なデザインを決定。
AIは、ユーザの好みを分析すると共に、色彩工学や人間工学といった膨大な知識を活用して、新しいデザインを生み出します。Webデザイナーは将来的には不要となるか、ディテイルの調整のみを行う職種へと変化するでしょう。
開発(コーディング)・テスト
サイトの仕様が複雑な場合は、外部仕様書や内部仕様書といった設計書を作成。
HTML,CSS,JavaScript等のプログラミング言語を用いて、ユーザインターフェイスを実装する。サイトの仕様によっては、コンテンツを動的に表示するバックエンドを実装。
テスト計画書・仕様書を作成し、モジュールテスト・統合テスト・総合テストなどを実施。テストを自動化するためのプログラムが必要となることも。
ノーコード・ローコード開発といった技術の進展により、AIが自動でコードベースを作成。パフォーマンスやセキュリティも完璧な状態に。
コード生成の過程でテストもデバッグも自動で行われるため、テストの工程は実質不要となる。
AIの発展により、プログラマーは不要となる可能性が高いと見ています。残るとすれば、機能のカスタマイズや改良点を、AIへフィードバックする程度の役割でしょう。
サーバー構築・リリース
クライアントへの要件のヒアリングを行い、サーバー構成図を作成。
ドメイン・サーバーの契約を行い、サーバーを構築。要件によっては、各種監視、スケーリング、自動バックアップ等の高度な設定が必要。
AIに必要な情報を伝えると、サーバーが瞬時に構築されサイトが公開される。
こちらもインフラやサーバーエンジニアは不要となり、AIがサーバー構築からサイト公開までを全て自動で実行してくれる様になります。
保守・運用
サイトの定期的な更新、バグ修正、セキュリティ対策を行う。
アクセス解析結果やVOCをもとに、改善点を見つけて継続的に改良を行う。
AIがサイトのパフォーマンスやサーバーの稼働状態を常に監視し、問題が発生する前に予防的な対応を実施。
AIがユーザー行動、コンバージョン率、他の重要な指標を分析し、最適化のためのアクションを提案、実施。
少し極端な表現もありますが、プロマネもデザイナーもSEも不要となる未来が見えました。AIとの対話だけで、思い描くサイトが迅速に、コストをかけずに生成できてしまいます。もちろん、パフォーマンスやセキュリティも最適な状態で提供されます。そんなサービスがそう遠くない未来に実現するでしょう。
以上を踏まえ、弊社もWeb制作現場でAIをどう活用すればいいか、真剣に向き合い考えていきたいと思います。今後の進化にご期待ください!